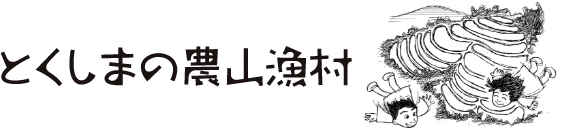祭りを元気にできたら日常も活気づく
担ぎ手を募って続けていきたい
毎年10月に行われる日和佐八幡神社の秋祭り。1年の豊漁豊作を祝って、「ちょうさ」と呼ばれる伝統の太鼓屋台が町内を練りまわる。この文化を次世代に守り継ごうと尽力するのが「日和佐ちょうさ保存会」。2010年の発足以来、フォトコンテストの開催やカレンダーの販売、子どもたちへの太鼓教室など、さまざまな活動に取り組んできた。
「とくしま農山漁村(ふるさと)応援し隊事業」には2012年から参加。地元高校の相次ぐ閉校や高齢化により、担ぎ手不足がいよいよ深刻化したことを受けての決断だった。「応援し隊事業を利用すると、企業と県を介して担ぎ手を募集できるので、お互いの安心感にも繋がると思います」と外礒さん。毎年、地元と町外からの参加者のそれぞれに心得をレクチャーし、事故やトラブルが起きないよう気を配る。
例年、協働パートナーと活動するのは秋祭り当日。重さ約1tのちょうさを50~60人で担いで、境内を練り歩いたのち大浜海岸へ(御浜出)。8地区の屋台が浜辺にずらりと出揃うと、ふたたび神社へと帰っていく(御入り)。なかには海へ飛び込む太鼓屋台もあり、大きな盛り上がりを見せる。4年ぶりの通常開催で「やっといつもの祭りが戻ってきた」と気合十分で迎えた今回。“赤ハッピ”と呼ばれる町外からの担ぎ手にも60人以上の参加があったという。
協働パートナーは「おってくれな祭りが成り立たない、ありがたい存在」と外礒さん。「以前は担ぎ手不足でちょうさが上がらなかった地区が、応援し隊の皆さんのおかげで、今では一番活気づいていますよ」と笑う。「なかには、毎年のように来てくれて、町の人と顔なじみになっている方もいる。特に松本コンサルタントの社員さんからは、地籍調査で日和佐を訪れたときに『あれ?秋祭りに来てくれていたよね』と再会することがあると聞いています」。
現在は年に1回、秋祭り当日だけの交流だが「たとえば道具の手入れや地区の忘新年会など、別の日にも一緒に活動できたら、さらに関係が深まって、祭りにもより親しみをもって参加してもらえるのかな」と構想する。「僕らにとっては日常があって祭りがあるので、ふだんのコミュニケーションがその2日間にギュッと凝縮される。本来なら町が元気だから祭りが活気づくんでしょうけど、町の人口がどんどん減っていくなかで、なんとか祭りを元気にできたら、日常も活気づくと思うんです。そのためにもやっぱり、町外から担ぎ手を受け入れながら続けていきたいですね」。

秋祭り当日は日和佐ちょうさ保存会が参加者に赤いハッピを貸し出す。町外からの参加者が一目でわかり、地元参加者もサポートしやすい。

大きな掛け声とともにちょうさを持ち上げる。担ぎ手の熱気に圧倒される。
※上記の写真と文章は、令和5年11月1日発行の月刊タウン情報トクシマ11月号より、許可のもと引用されています。
|